江戸の浮世絵師として世界的に評価されている、葛飾北斎(かつしか ほくさい)。
その名前や『富嶽三十六景』などの作品は知られていますが、実は改名を何度か行っています。
今回は北斎について、改名の詳細と本名、生涯と性格のまとめ、さらに引っ越しのエピソードを見ていきましょう。
葛飾北斎のプロフィール
本名:川村鉄蔵
生年月日:宝暦10年9月23日(1760年10月31日)
死没:嘉永2年4月18日(1849年5月10日)
身長:推定180cm
出身地:武蔵国葛飾郡本所割下水(現在の東京都墨田区)
葛飾北斎、改名の数がすごい
まず北斎の改名について、詳細を見ていきます。
実は北斎は、画家としての活動名である雅号を30回も変えていました。
改名した中でも知られているのが、画狂人、錦袋舎、百琳などです。
これらをあくまで副次的な名前として使っていただけで、正式に改名したわけではないという説もある一方、弟子に名前を譲るために何個も雅号を用意していたという研究もあります。
雅号は弟子に譲ることで収入になったそうなので、貧しかった北斎はあまり雅号に執着せずお金に換えていたのでしょう。
最も有名な「北斎」という雅号は、「北斎辰政」の略称で、北極星と北斗七星を神になぞらえた北辰妙見菩薩の信仰に由来しているそうです。
本人にとって、北斎という名前すら、自分の一部を表すだけのものに過ぎなかったのかもしれません。
北斎の本名は?
北斎がたくさんの改名を重ねたことを考えると、もはや本名すらわからなくなってしまいそうですが、正式な本名は何なのでしょうか。
川村家に生まれた北斎は、幼名が時太郎だったため、川村時太郎が当初の本名だったことになります。
しかし何らかの理由で4歳のときに、江戸幕府の鏡職人である鏡磨師・中島伊勢の養子となりました。
さらにその後、鉄蔵と正式に改名したようですから、「中島鉄蔵」が成人後の本名だったのではないでしょうか。
ただし中島家の家督を継いで鏡磨師にはならず、19歳のときに、役者絵で知られる天才絵師・勝川春章に弟子入り。
【桃山・江戸の華とわびの作品ご紹介!】
2019年09月27日(金) – 10月28日(月)
重要文化財 婦女風俗十二ケ月図
勝川春章肉筆浮世絵の中でも代表的な傑作となるこの揃物は、春章の最も脂の乗った天明期(1781~89)の作で、月々の季節感や行事を各図に背景として見事に取り入れています。 pic.twitter.com/UGf43uwTXN
— MOA美術館 エムオーエービジュツカン (@moa_museum) October 8, 2019
以降は貧しいながらも、七味唐辛子の販売などの副業をしながら絵師の道を歩みました。
世界大百科事典によると、本名は「川村鉄蔵」とあり、もしかすると家督を継がないと決めた段階で旧姓に戻したのかもしれません。
その後は師匠から雅号として勝川姓をもらい、勝川春朗の名前で挿絵や錦絵を描く絵師としてデビューしています。
勝川派にはのちに破門されたとも、北斎の方から決別したとも言われていますが、音の響きからすると「葛飾」は「勝川」がもとになっているのでしょう。
北斎の生涯と性格
ここからは、絵師になった後の北斎の生涯と、その性格について見ていきましょう。
勝川派を離れた北斎は、江戸琳派の俵屋宗理という絵師の影響を受け、2代目俵屋宗理を名乗ります。
この時期に狂歌絵本『狂歌歳旦 江戸紫』の刊行、美人画技法の修得などに取り組みました。
34~35才のころ、勝川派から離脱し、光琳風の肉筆画を描く江戸琳派の一門俵屋宗理を襲名する。 pic.twitter.com/HDsmJSC5S5
— ☀️ (@ynamasu) June 16, 2013
1799年ごろから、絵師として売れ始め、北斎という雅号を用いるようになります。
以降は流派に属さず、孤高の絵師として『仮名手本忠臣蔵』、『東海道名所一覧』といった名作を次々に手掛けていくのです。
待ち合わせまで時間があったので「すみだ北斎美術館」へ。
さすが北斎先生だけあって、一歩入った瞬間から私のハートを鷲掴み♡と、横にいた二人連れの女性がこんな会話を。
「雪掻きしてるんだね」
「みんなでやるんだね」見ている絵→『仮名手本忠臣蔵 十一段目』 pic.twitter.com/aXJWcfLwV7
— 加門七海 (@kamonnanami) December 15, 2016
88歳近くなるまで生涯現役で絵師を続け、「あと10年、せめて5年生きられたら、真の絵師になれる」と語ったという逸話があります。
それだけ絵に情熱を傾け、現状に満足することのないパワフルな人物だったことがわかりますね。
そんな北斎の性格は、まさに天才のイメージ通りのものでした。
絵以外のことには執着せず、家はごみだらけで、生活の面倒は弟子が見ていたようです。
生活に関心がないのは周囲にとって困りものですが、同時に酒やたばこといった嗜好品にもまったく執着がなかったようで、それが長寿の秘訣だったかもしれませんね。
一流画家になってからもお金に無頓着で、あるだけ使ってしまっていたため、生涯貧しいままだったようです。
さらに短期で喧嘩っ早く、トラブルには事欠きませんでした。
歌舞伎役者の三代目尾上梅幸(おのえ ばいこう ※のちの菊五郎)が北斎に絵を依頼しますが、北斎宅があまりに不潔だったので絨毯を敷いたところ、北斎は「無礼だ」と言って梅幸を相手にしなかったそうです。
相手が有名人であろうと、身分が高かろうと物おじしなかったのは、あくまで自分中心と考えていたのかもしれません。
わがままで自信過剰な点も、いかにも天才らしいですね。
引っ越しのエピソード
北斎の家がごみ屋敷同然だったのは先述の通りですが、住めないほど汚くなった場合はその度に引っ越しをしていたそうです。
引っ越し回数は、何と93回にも上ります。
絵を描くことだけに集中していたため、当然自炊はせず、惣菜を買うか出前を取っていました。
食べ終わると、包み紙や食べかすは部屋に放置していたので、部屋の中はごみ溜めだったそうです。
酒を飲まない分、大層な甘党だったと言いますから、お菓子の包み紙などが床を埋め尽くしていたに違いありません。
掃除すればいいものを、そのような常識的感覚がない北斎は、住み心地が悪くなれば引っ越しをしたのです。
娘で絵師のお栄だけは、そんな父と同居していましたからごみ屋敷も平気だったのでしょう。
親子そろって変わり者の天才絵師だったと言えますね。
今回は葛飾北斎についてまとめました。
優れた作品だけでなく、ユーモラスな逸話でもファンの心をくすぐる絵師なのでしょう。
関連記事
葛飾北斎の娘・お栄も浮世絵師、辰女は正体不明。息子は2人で子孫がいる?妻は2人

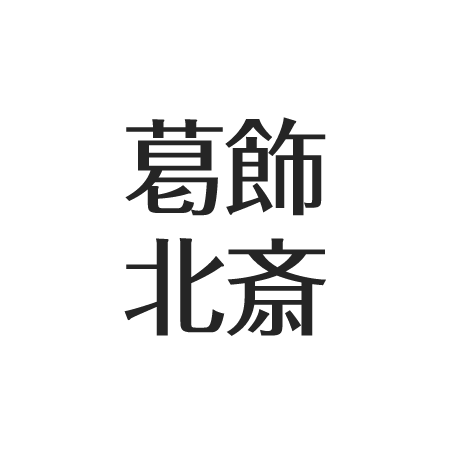
コメント