日本美術史に輝かしい名を刻む絵師・葛飾北斎(かつしか ほくさい)。
『冨嶽三十六景』などの傑作を多く描き、その作品数は3万点以上とされています。
ただ日本人にとっては、「赤富士」と「巨大な波」のイメージしかないかもしれません。
それに比べて海外ではかなり高く評価されていますが、その理由は何でしょうか。
また後進の画家に影響を与えたと言われていますが、具体的にどのような影響があったのかも気になりますね。
今回はこれらの疑問を見ていきつつ、天才と呼ばれる絵師の構図、作品の特徴を一挙にご紹介します。
なぜ北斎が、そこまで偉大な絵師と呼ばれるのかひも解いていきましょう。
葛飾北斎のプロフィール
本名:川村鉄蔵
生年月日:宝暦10年9月23日(1760年10月31日)
死没:嘉永2年4月18日(1849年5月10日)
身長:推定180cm
出身地:武蔵国葛飾郡本所割下水(現在の東京都墨田区)
葛飾北斎に対する海外の評価。後の画家への影響は?
まずは北斎が海外でどのように評価されているのか、また後進の画家へどれほどの影響をもたらしたのかを見ていきましょう。
北斎は今でこそ偉大な画家として扱われていますが、実は生前は火事で一文無しになるなど、赤貧に苦しんだこともありました。
金遣いが荒く、奇人・変人とも言われていた北斎ですが、海外では、『モナリザ』のレオナルド・ダヴィンチに匹敵する大画家として扱われているようです。
1998年にはアメリカのライフ紙が発表した、「19世紀に偉大な業績をあげた世界の人物100人」に日本人として唯一選ばれるなど、高い評価を受けていますね。
北斎作品が海外で知られたきっかけは、19世紀後半にさかのぼります。
パリ在住の銅版画家ブラックモンが、友人の家で日本からの輸入品の磁器を見ていたとき、緩衝材に使われていた北斎の絵に目をとめたとされています。
これが北斎発見のきっかけかどうか、今では疑問視されているものの、緩衝材に使われても不思議ではないほど当時の『北斎漫画』に対する扱いが軽かったことがわかりますね。
パリ旅行の目的は、欧州の芸術家達が #北斎 に注目するきっかけとなった”北斎漫画”の初編出版200年を記念した史上最大規模の「北斎展」。19世紀半ばに日本からの陶器の梱包で詰め物に使われていた”北斎漫画”を版画家フェリックス・ブラックモンが偶然見たことが始まりです。 https://t.co/24i3eGg6yt pic.twitter.com/0NHsbaSd11
— Souvenir Inoubliable (@SouvenirInoubl1) November 20, 2020
従来の西洋絵画は、聖書や神話を描くことが一種の規則でもありました。
だからこそ、北斎の描く庶民の姿や自然の景色など、何気ない風景が芸術として成り立っている浮世絵に対する衝撃は大きかったのでしょう。
さらに『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』では、“グレートウェーブ”と呼ばれる、かぎ爪上の大波が富士山を飲み込まんばかりの迫力で描かれていることも驚きだったはず。
これまでの西洋絵画の概念を大きく覆す題材と、迫力満点の絵に、海外のコレクターは興奮したのでしょう。
北斎作品はコレクターだけではなく、画家たちにも影響をもたらします。
聖書などの決まりきった題材ではなく、庶民や風景を描く画家が現れるのもまさにこの頃。
ゴッホ、ゴーギャン、セザンヌ、ロートレックといった画家たちがその典型例です。
彼らが美術界に革新をもたらすうえで、北斎という存在が不可欠だったことは間違いないでしょう。
天才絵師の構図について
では北斎が天才と言われるゆえんと、そこまで海外に受けた理由を、もう少し詳しく構図から考えてみましょう。
西洋美術は伝統的に、左右対称(シンメトリー)を重視していました。
しかし北斎の構図は左右非対称、さらに対象物の一部は拡大され、絵画とは思えないほど圧巻の迫力を描き出しています。
北斎が描いた九段坂。遠近法で描いてるし、サインが洋風なのがすごい。岸田劉生も見たんだろうな。電車を通す時に勾配が削られたらしいけど「坂のある東京」を記録しておこうと思ったのかもしれない。江戸っ子、劉生として。 pic.twitter.com/BDlB9f48YX
— ナカムラクニオ(6次元) (@6jigen) August 27, 2020
巨大な波が山を覆わんばかりの勢いで迫り、船に乗った人々はまるでアリのように小さく描きこまれるなど大胆な遠近法が、写実を重んじる西洋美術界に衝撃をもたらしたのでしょう。
葛飾北斎の代表作である、「神奈川沖浪裏」の習作と呼べるような一作。遠近法の使い方が「神奈川沖浪裏」とは違います。 pic.twitter.com/dDInpSkiYF
— 浮世絵_Love (@ukiyoelovers) November 22, 2020
日本でも歌川広重など優れた絵師は多いものの、北斎ほど大胆な構図を描く人物は類を見ません。
作業部屋は散らかり放題で、生活に必要なことは周りに任せていた点も含めて、「天才」の名にふさわしい人物だったのでしょう。
北斎作品の特徴まとめ
北斎は日本よりも、海外でその大胆な構図と庶民的な題材で高く評価された画家です。
浮世絵という存在自体が、その鮮やかな色彩表現も相まって、海外で受けたというのも大きいでしょう。
だからこそ北斎は、海外ではある意味、現実離れしたシュールレアリスム的な画家として受けたのかもしれません。
しかし北斎の特徴は何といっても、その大胆な構図にもかかわらず、同時に緻密でリアルに対象を描き上げている点にあります。
人物画などはその衣装や顔のしわ、動きを詳細に観察していることがわかりますし、風景画についてもあり得ない構図に見えながら細部はとてもリアルに描いているのです。
だからこそ、単に一時だけ流行するような奇抜な作品ではなく、時代を超えて受け入れられる作品と言えるのが北斎作品なのです。
今回は葛飾北斎の作品についてご紹介しました。
天才画家の表現は、これからも国境と時代を超え、見る人に衝撃を与え続けていくことでしょう。
関連記事
葛飾北斎の娘・お栄も浮世絵師、辰女は正体不明。息子は2人で子孫がいる?妻は2人

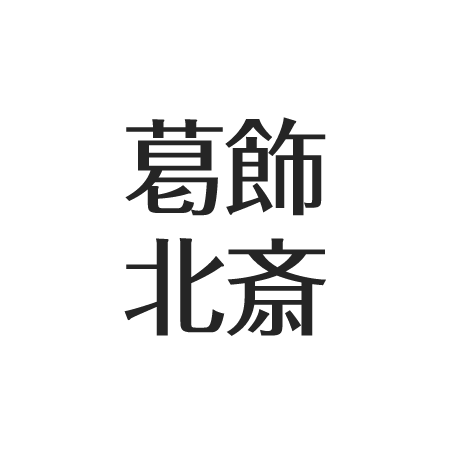
コメント