「人生100年時代」といわれる現在、「定年退職者の星」としてシニア世代から関心が高まっている伊能忠敬(いのうただたか)。
わが国初の実測日本地図をつくった人物として有名ですが、本格的に勉学に取り組み、測量に着手したのは隠居したあとのことでした。
日本全国、およそ4万キロを踏破して偉業を成し遂げた伊能忠敬とはどんな人だったのか、性格にも注目して探っていきたいと思います。
また「伊能図」に対する当時の海外の反応や、地図づくりのきっかけとなった天文学についてもまとめました。
伊能忠敬のプロフィール
本名:神保三治郎
生年月日:1745年2月11日(延享2年1月11日)
死没:1818年5月17日(文化15年4月13日)
身長:160cm前後
出身地:上総国山辺郡小関村(現在の千葉県山武郡九十九里町小関)
地図をつくった人、伊能忠敬とはどんな人?
17年の歳月をかけて蝦夷地(北海道)から九州までを測量して歩き、「大日本沿海輿地全図(だいにほんえんかいよちぜんず)」、通称「伊能図」を完成させた伊能忠敬。
「地図をつくった人」というイメージが先行するのは当然のことですが、もともと商人であり、天文学者の顔ももっていました。
生まれは延享2年(1745年)、現在の千葉県の九十九里町。
17歳で伊能家の婿養子に迎えられ、10代目当主に。
伊能家は、代々名主(なぬし)を務める有力な商家で、忠敬は商才を発揮して家業を発展させるとともに、名主や村方後見として郷土に尽力します。
五十にしてまた歩き始める魂#伊能忠敬 #富岡八幡宮 pic.twitter.com/q46QDTZQGl
— Isuke (@shirononagori) November 5, 2020
人生の転機は49歳で訪れます。
若い頃から数学や天文書を好んでいた忠敬は、本格的な勉学を志すようになり、49歳で家督を息子に譲って隠居。
翌年には単身江戸に出て、幕府天文方・高橋至時(たかはしよしとき)に弟子入り。
天文方とは、太陽や月の運行を観測して暦をつくる部署のこと。
やがて忠敬は、正確な暦をつくるために必要な緯度1度の距離を知りたいと思うようになりました。
これが長年にわたる全国の測量へと発展していきます。
55歳での蝦夷地の実測を皮切りに、計10回におよぶ全国の測量が終わったのは71歳の時。
ちなみに、距離を計測するために用いたのは歩数でした。
忠敬は自分の歩幅を測り、一定の幅で歩けるように訓練していたとのことです。
伊能忠敬の生き方には、人間は何をするにも遅すぎることはないのだと教えられます。
隠居とは現役を退くことですから、今でいうと定年退職後に大学に入学するようなもの。
江戸時代には高齢者とみなされたであろう50歳から第二の人生をスタートさせた心意気は、お手本にしたいですね。
伊能忠敬の性格は測量向きだった?
17年間、およそ4万キロを測量しながら踏破するのは若者であっても難しいでしょう。
偉業を成し遂げられるか否かは精神や情熱によるところが大きいことをあらためて感じます。
伊能忠敬は好奇心が旺盛で根気強く、几帳面な性格だったと伝えられています。
測量に適した性格だったといえるかもしれませんね。
また厳格な一面もあり、測量期間中に地元の人々に無礼を働いたり、お酒を飲んだりした隊員には相応の処分をするなど規律を重んじていたとのこと。
内弟子の1人だった息子の秀蔵も特別扱いはしませんでした。
もともと商人であったことから、家人の金銭の無駄使いに厳しいところもあったよう。
その一方で、飢饉や自然災害で困窮した人々には惜しみなく援助の手をさしのべていました。
伊能忠敬は、意味のあることには大金を投じるけれども、意味のない散財はしないという、合理的な考え方をしていたことがうかがえます。
才能に恵まれた人物であったことは疑いようがありませんが、聖人君子というよりは、よい面も悪い面もある普通の人間だったのではないかと思われます。
「伊能図」に対する海外の反応
伊能忠敬が没して3年後、弟子たちによって「大日本沿海輿地全図」が完成します。
忠敬が割り出した緯度1度の距離は28.2里(110.75キロ)であり、現代の測定値との誤差は約1000分の1と、当時としては驚異的な正確さでした。
のちに日本にやってきた西洋人たちは、地図の精度の高さに驚きます。
日本人を未開の野蛮人のようにとらえ、文化的後進国と見下していた国に優れた地図があったのですから、空恐ろしく感じたかもしれません。
文政11年(1828年)には、ドイツ人医師シーボルトが忠敬の地図を入手したことが発端となって大騒動に発展。
というのも、地図の海外への流出は国家機密の漏洩と同じことだったからです。
令和3(2681)年8月7日
(天保暦 7月10日)『大日本沿海輿地全圖』㊗完成200年#大日本沿海輿地全図 #伊能図#伊能忠敬 #地図 #日本地図 #測量#文政4年 #1821年 #2世紀#香取市 #九十九里町 #千葉県 #今日は何の日 #歴史 #日本史 pic.twitter.com/0rcDs4rEeO
— 孤軍奮鬪 (@yowoureuhibi) August 6, 2021
諸外国に国土の地形を知られれば、軍事的な危険性が高まるというわけですね。
「伊能図」の正本は江戸時代を通じて幕府によって厳重に守られていました。
伊能忠敬は天文学を学んで測量に活かした
伊能忠敬が隠居して江戸に移り住んだ時に学んだのは暦学と天文学です。
旅行の際には、隠居する前から独学で学んでいた暦学を用いて、各地で測った方位や天体観測で求めた緯度などを旅行記に記していました。
江戸で師事した高橋至時は天文学者で19歳年下。
事業で成功をおさめ、社会的地位も高かった忠敬が31歳の若者に教えを請うたことからも学びへの情熱がうかがえますね。
天体観測のための機器も購入し、自宅に天文台をつくって、寝る間を惜しんで天体観測や測量の勉強に打ち込んでいたようです。
忠敬が観測していたのは太陽の南中、日食、月食、惑星食など。
こうして天文学を学んだことが測量に活かされていきました。
従来の測量法に天体観測を組み合わせて入念に測量することで精度を高めていったのです。
「人生を二度生きた男」ともいわれる伊能忠敬。
わが国最初の地図づくりは50歳からスタートした一大プロジェクトでした。
私たちも年齢を言い訳にせず、新しいことに挑戦していきたいですね。
伊能忠敬の家系図。子孫はキャディー&カフェ経営者。生家と旧宅について

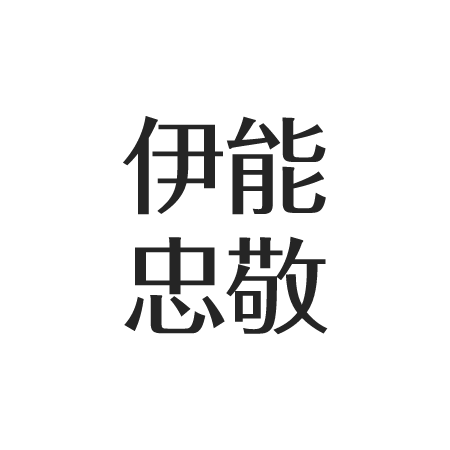
コメント