「オダサク」の愛称で親しまれた小説家の織田作之助(おだ さくのすけ)。
代表作『夫婦善哉』にも登場する、彼がこよなく愛したカレーを紹介します。
また彼の子孫および彼が織田信長の子孫であるという情報、ゆかりの地・大阪にある関連スポットを確認。
さらに同じ「無頼派」の小説家だった太宰治、坂口安吾との友情エピソードも見ていきましょう。
織田作之助のプロフィール
本名:織田作之助
生年月日:1913年10月26日
死没:1947年1月10日
身長:約177cm
出身地:大阪府大阪市南区(現在の天王寺区)
最終学歴:第三高等学校文科甲類(新制京都大学教養部の前身)退学
織田作之助が愛した自由軒の名物カレー
作之助は大阪の難波にある老舗洋食店「自由軒」のカレーをこよなく愛していました。
1913年の今日は日本の小説家、織田作之助が生まれた日です。通称「オダサク」。大阪「自由軒」の「元祖混ぜカレー」が好物でした。自由軒本店には「トラは死んで皮をのこす。織田作死んでカレーライスをのこす」と書かれています。 pic.twitter.com/uoPanX6odq
— 愛書家日誌 (@aishokyo) October 25, 2020
いつも注文していたのは、ルーがご飯にまぶされた「名物カレー」。
自由軒の名物カレー🍛緊急事態宣言中はお休みされてて、食べれないと余計に食べたくなるもので😂今日やっと🤗🤗🤗 pic.twitter.com/wd7KQ7Wpws
— さいさん🦏🦏🦏 (@ooguiinu) October 6, 2021
一般的なカレーはご飯にルウがかけられていますが、名物カレーはご飯とルウをあらかじめ混ぜ込んであります。
具材は牛肉と玉ネギだけというシンプルなルウ。
トマトピューレの入ったソースと牛スジのブイヨンによる旨みが魅力です。
これを混ぜ込んだご飯の上には、生卵が乗っています。
さらにソースをかけると旨みが増すようですね。
一度食べると病みつきになる人も多い、庶民派グルメと言えます。
6年ぶりに自由軒の名物カレーいただきまーす(*´∀`*) pic.twitter.com/Xbn2Yot200
— sola (@sola_0428) October 3, 2021
作之助はほとんど毎日自由軒に通い、名物カレーを食べていました。
カレーを食べながら構想を練ったのが、代表作『夫婦善哉』です。
作品ではヒロインの蝶子が名物カレーを食べるシーンが描かれています。
『夫婦善哉』を読んで、「名物カレーを食べてみたい」と考えた人は多くいるでしょう。
店内には作之助が店にあげたという、作品執筆中の自身が映った写真が飾ってあります。
『夫婦善哉』で売れっ子作家になる前から通い続けた店に、恩返しをするため、写真を遺してくれたのかもしれませんね。
織田作之助に子孫はおらず、織田信長の子孫でもない
ところで作之助が織田信長の子孫という情報があるようですが、本当なのでしょうか。
確かに家紋が「織田木瓜」という共通点があるため、可能性はありそうですよね。
京都 『#阿弥陀寺』 信長忌
織田家の家紋
「#織田木瓜(おだもっこう)」受付で、頂いた白い紙包み。中を開けると直径4㎝くらいのとても可愛らしい落雁がふたつ。織田家の家紋、織田木瓜でした。何だか嬉しい😙
これはちょっとマニアックかも…ですが、お宝にします🤗
流石の私も食べません🙄 pic.twitter.com/lRf0e0tbOK— たみちゃん (@osuka_yst) June 3, 2018
ただ作之助が信長の子孫であるという確証はないため、おそらく関係はないのでしょう。
信長の子孫と言えば、17代目子孫を自称する、フィギュアスケート選手の織田信成さんが有名ですね。
また子孫と公認されているのは、ジュエリー会社に勤務する織田茂和さんでした。
ちなみに作之助は早世しており、自身の子孫は残していません。
もし信長と作之助の血を継ぐ子孫がいれば、何らかの業績を残していたかもしれませんね。
織田作之助のゆかりの地・大阪
商人の街として知られる大阪。
作之助の父・織田鶴吉も商いをしており、仕出屋「魚春」の店主でした。
今でも中央区上汐1丁目の一画に、当時の家並が残っているそうです。
生家があった場所の近くには、「難波大社 生國魂神社」があります。
正面に「千鳥破風」「すがり唐破風」「千鳥破風」と呼ばれる3つの破風を備えた、珍しい「生國魂造」様式の神社です。
趣向を変えて昔の絵葉書、空襲で焼失した生國魂神社の旧社殿。本殿と幣殿の屋根が一つの流造で葺き下ろされ、正面の屋根に千鳥破風・すがる唐破風・千鳥破風の三破風を据えた生國魂造。戦後、鉄筋コンクリートで再建されたが、拝殿と回廊に囲まれ、外からその豪壮な姿を見ることは難しい。 pic.twitter.com/K6a9aGUu3y
— こまいぬ@御朱印研究家 (@kokon_komainu) October 6, 2016
神社の中には作之助の銅像も建てられています。
生國魂神社にある織田作之助像。すぐ近くの生魂小学校の前に生家があり、旧制府立高津中学校卒業ということなので、十代後半までこの付近をうろついていたんでしょう。 pic.twitter.com/YXFsmdo2Tp
— 半夏生 (@osaka_map2) April 10, 2019
また同じく大阪出身の文豪・与謝野晶子と共に、ゆかりの石碑が大阪エリア各所に存在します。
夫婦善哉の石碑も探せばよかったね。多分お不動さんの裏辺りにあったんだろうけれども。
織田作之助『木の都』の石碑と口縄坂。
堺で見掛けた桜とこいのぼり。
与謝野晶子生家跡。 pic.twitter.com/pZXyEqWu3W— MARIAN † ROSE×魔法商会Cabbit (@LELsorayu) April 5, 2018
大阪を散策するときは、作之助の生まれ育ったエリアを歩いてみると、彼に思いを馳せられるはず。
休憩時間には自由軒で名物カレーを食べれば、きっと文豪気分になれますよ。
織田作之助は太宰治&坂口安吾と同じ無頼派の作家
作之助は昭和初期を代表する小説家である、太宰治と坂口安吾と共に、「無頼派」と呼ばれていました。
別名「新戯作派(しんげさくは)」で知られる作家の一群のことです。
いずれも敗戦後の混乱期、反道徳的な表現を使って、既成文学をはじめとした権力側へ対抗した人々でした。
3人はそれぞれ反権力的という点で共通していたのです。
無頼派の3人は仲良し
作之助、太宰、坂口は実際に交流があり、お互いの実力を認め合っていたようです。
3人全員が初めて顔をそろえたのは、1946年11月22日に銀座の実業之日本社で行われた座談会でのこと。
評論家の平野謙が司会を担当し、「現代小説を語る」というテーマで議論が展開されました。
座談会終了後は、企画担当の倉崎嘉一も加えた5人で、バー「ルパン」へ繰り出しました。
さらに3日後の25日には再び作之助、太宰、坂口の3人で対談し、やはりルパンへ出かけたそうです。
太宰治・坂口安吾・織田作之助の鼎談「歓楽極まりて哀情多し」(『読物春秋』昭和24年1月)です。鼎談の日付は昭和21年11月25日。織田作の喀血と死により予定の『改造』に掲載されず、初出時に生きていたのは安吾だけでした。ちなみに終了後3人は、銀座のバー「ルパン」であの有名な写真を撮っています。 pic.twitter.com/nbe2wOBnNx
— 初版道 (@signbonbon) January 30, 2021
同じ無頼派の作家同士、仲間意識が強かったようですね。
25日に写真家・林忠彦が、後世に残る作之助たちの有名な写真を撮影しています。
1946年(昭和21年)。銀座のバー「ルパン」での織田作之助です(1枚目)。
これを撮った林忠彦に「おい、オダサクばっかり撮ってないで俺も撮れよ」と絡んできたのが太宰治で、ついでの気持ちで彼を撮ったのがこの有名な写真です(2枚目)。 pic.twitter.com/uXgUjoIvoJ— 戦前~戦後のレトロ写真 (@oldpicture1900) June 27, 2017
改めて写真を見ると、仲間同士の飲み会の楽しそうな雰囲気が伝わってきますね。
太宰と坂口は作之助のために追悼文を執筆
無頼派の3人が仲良く交流できたのは、わずか数か月ほどの間でした。
対談から約1か月後の翌1947年1月10日、作之助は肺結核により33歳の若さで亡くなります。
東京新聞の文化欄には太宰による追悼文「織田君の死」が掲載されました。
追悼文によると、作之助は生前から「死ぬつもり」で日々を生きていたようです。
文学も酒も思う存分楽しむ作之助の姿から、太宰は内に秘めた悲哀を感じ取っていたのでしょう。
初対面のとき「なんてまあ哀しい男だろう」と考えたという太宰。
このとき作之助はすでに体調を崩して、死を覚悟しながらも、作家業に全力を注いでいたに違いありませんね。
また2019年には70年ぶりに、坂口が作之助のために書いた追悼文も発見されました。
通説では、坂口は作之助の死に際し酒を飲んだ程度で、追悼文を残していなかったとされてきたのです。
しかし仲間の死を悼む本格的な文章を残していたことがわかり、多くの無頼派ファンが衝撃を受けたようですね。
坂口安吾による織田作之助追悼文 約70年ぶり発見 :日本経済新聞 https://t.co/N8RfwNqv4O
全フォロワー読んで。。。— 合鴨火炎放射器 (@FrakPhemto) February 15, 2019
追悼文では作之助のことを「才能の片鱗を残しただけ」で死んでしまったと表現。
いずれ偉大な作家になりえただろう若者の才能を、心から惜しんでいたことがうかがえます。
対談文と追悼文を読むだけでも、3人の友情が感じられ、目頭が熱くなるかもしれませんよ。
関連記事
太宰治の三鷹、鎌倉との縁。愛した着物、万年筆、ウイスキーのこと

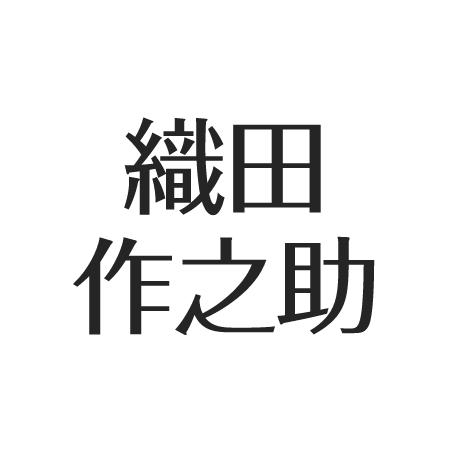
コメント