元長州藩士で、内閣総理大臣や陸軍参謀総長などを歴任した山縣有朋(やまがた ありとも)。
今回は山縣の子孫が今でも続いているのか、家系図から確認しましょう。
また彼が邸宅の敷地内に作庭した、椿山荘の情報を見ていきます。
さらに渋沢栄一原作の『漫画版 論語と算盤』における、山縣の登場シーンもご紹介します。
山縣有朋のプロフィール
幼名:辰之助
本名:山縣有朋
生年月日:1838年6月14日(天保9年閏4月22日)
死没:1922年2月1日
身長:推定170cm
出身地:阿武郡川島村(現在の山口県萩市川島)
最終学歴:松下村塾
山縣有朋の子孫を家系図で確認
まず山縣の子孫を家系図から確認しましょう。
山縣は、長州藩の庄屋の娘だった石川友子と結婚しました。
彼は妻に深い愛情を注いだようです。
明治時代は、伊藤博文をはじめ、女性問題のスキャンダルにまみれた閣僚が多い時期でした。
山縣にも妾はいたものの、派手な女遊びはしていなかったようです。
当時の政治家の中では、比較的実直な性格だったのでしょう。
結婚当初は、高杉晋作が創設した「奇兵隊」の一員として戊辰戦争に参戦していたため、妻との時間を過ごせなかったそうです。
しかし明治時代に入ると、落ち着いて夫婦生活を営むようになりました。
長州 #赤禰武人 の名誉回復に反対したと言われる #山縣有朋
#奇兵隊 統監の赤禰と軍監よ山縣の関係であった。
赤禰に逆らった場面は見られないが #高杉晋作 の功山寺挙兵にも山縣は内心は高杉派だったのかも
この人は長生きが一番の能力だったのでは pic.twitter.com/e3F3dHVsfH— かいもうし (@mtoshi88230) October 8, 2019
2人は円満に過ごし、3男4女をもうけています。
しかし7人の子供のうち、6人が夭折。
友子は相次いで子供を亡くし、仏教に救いを求めるようになったそうです。
愛する子供を6人も亡くしたのであれば、誰でも希望を失うに違いありませんね。
さらに山縣家にとっても子供の死は大きな問題でした。
次女の松子しか生き残らなかったため、跡継ぎが途絶えてしまったのです。
そこで山縣は、姉である壽子の次男・伊三郎を養子に迎え、山縣公爵家を継がせました。
伊三郎は、徳島県知事や枢密顧問官などを歴任します。
以降は伊三郎の息子・有道が跡を継ぎ、宮中に勤めました。
彼の息子・有信は、栃木県矢板市の市長を務めた人物。
2023年現在の当主は、有信の息子で、有朋の養玄孫にあたる山縣有徳さんです。
会社経営の傍ら、有朋が開拓した「山縣農場」にある「山縣有朋記念館」で、祖先の功績を伝えてきました。
山縣有朋記念館(旧山縣有朋別荘)の右隣に
増築する形で昭和初期に建てられた「山縣睦邸」
現在も居住されている為、内見は不可。#栃木県 #矢板市 #近代建築 #歴史遺産 #山縣有朋 pic.twitter.com/o8HYLRZgwA— くまP🗾写真 (@kumasan_planet) September 2, 2019
有徳さんには、有成さんという息子もいます。
山縣家が順調に子孫を残してきたことがわかりましたね。
山縣有朋の邸宅、庭は椿山荘
山縣の邸宅は、東京都文京区にありました。
西南戦争の功績を讃えられた山縣が、年金740円を投じ、旧屋敷を購入。
神田川に面した小高い場所に庭園を作り上げました。
庭園のある場所は、南北朝時代から椿が自生していたため、「つばきやま」と呼ばれていたそうです。
山縣は古い名前にちなみ、作り上げた庭を「椿山荘」と命名しました。
彼の死後は、1948年に藤田興業(現在のDOWAホールディングス)が庭園を所有。
1万ほどの樹木が移植されたのち、1952年からは宴会場と結婚式場の営業が始まります。
1992年からホテル営業を開始し、2013年に「ホテル椿山荘東京」にリブランド、庭園もホテルと一体運営化しました。
邸宅は現存しておらず、跡地にはバンケット棟が建っています。
しかし立派な庭園は無料公開されており、椿や桜などの植物を鑑賞可能。
三重塔や、伊藤若冲が作った「五百羅漢」の石仏の一部も見学できます。
山縣有朋の邸宅だった椿山荘。隣の細川庭園と同じくこちらも無料。タダでこれだけの庭園を巡れるのは本当にお得!結婚式後の新郎新婦の撮影なども行われていていい雰囲気だった。 pic.twitter.com/FWmFnDYW0B
— gakudai (@tantake0205) May 25, 2019
ホテルの宿泊客だけでなく、周辺を散策する人や観光客も、自然豊かな庭園と歴史的建造物を楽しめるスポットです。
作庭が趣味だった山縣は、多くの人が自身の庭に集まる様子を、誇らしげに見守っているかもしれませんね。
山縣有朋が渋沢栄一の漫画に登場
大河ドラマ『青天を衝け』の主人公として話題になった渋沢栄一。
彼の名著といわれているのが、『論語と算盤』です。
実業家である渋沢栄一が、後進育成のために経営哲学を述べた、談話録として知られています。
論語の道徳に従った商売をし、利益は皆の幸せのために使うという考えから、経営と社会貢献の両立の重要性を述べました。
講談社が出版した漫画版の『論語と算盤』には、渋沢の元に、山縣が幽霊として現れるシーンがあります。
トランプ遊びで勝ち逃げした渋沢が部屋に帰ると、前年に死んだはずの山縣がいたのです。
「漫画版 論語と算盤」の原作者・渋沢栄一が2012年NHK大河「晴天を衝け」の主人公に。「漫画版 論語と算盤」では渋沢(右)と山縣有朋(左)の対決を軸に渋沢の思想に迫ります。 pic.twitter.com/d7pe62FQwW
— 講談社まんが学術文庫 (@man_gaku) September 11, 2019
漫画版の「論語と算盤」を購入〜。
正直論語と算盤とはあまり関係がなく、大河の渋沢栄一のガイダンスのような内容だった。
山縣有朋が幽霊として現れて、人望の厚い渋沢栄一と対象的に、ひがんでいる描写が面白かった。 pic.twitter.com/hueqnYBZeB— ponomaru スクラムマスター (@ponomaru0822) May 27, 2020
山縣は自分の葬儀の参列者が少なかったため、人望厚い渋沢をひがんで、「死んでも死にきれない」と発言。
以降はそれぞれの対話を通し、2人の人望に差が生じた原因が明らかになるのです。
渋沢は官僚を辞して実業家となり、得た利益を国民のために使いました。
しかし山縣は私欲に走る官僚だったため、人々から嫌われてしまったといいます。
実際、山縣の葬儀に参列したのは官僚や軍人ばかりで、国民から嫌われていたことがうかがえますね。
国のために奉仕しているつもりが、私欲に走ってしまう官僚はいつの時代にもいるはず。
だとすれば渋沢のように、官職を捨てた人物こそ、対等な立場から国民に手を差し伸べてくれるのかもしれません。
ただ山縣も国のために多忙な日々を送ったことは事実です。
葬儀の参列者が少ないからといって、悪人扱いしてしまうのは、やや気の毒かもしれませんね。
関連記事
高杉晋作、子孫と生家。家紋の誇り。妻、息子との関係とは
高杉晋作の死因は結核。おもしろきの意味、三味線好き。性格は感情的?

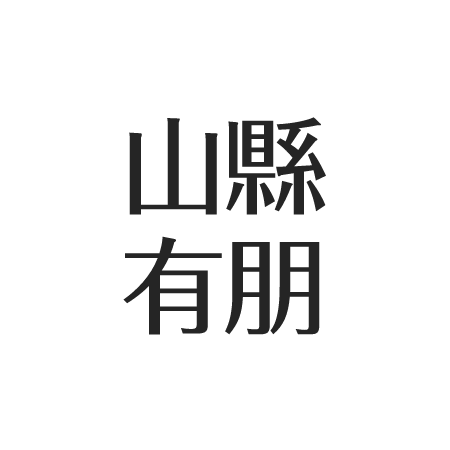
コメント