2017年に没後90年を迎えた芥川龍之介(あくたがわりゅうのすけ)。
大正文学の人気作家であった芥川の自死は当時の文壇はもとより、知識人にも大きな衝撃を与えました。
今回はその生涯や遺書に注目します。
また龍之介の死を嘆き、芥川龍之介賞を創設した友達の菊池寛や、同じく友達の谷崎潤一郎との文学論争についても取り上げます。
芥川龍之介のプロフィール
本名:芥川龍之介
生年月日:1892年3月1日
身長:不明
出身地:東京市京橋区入船町8丁目(現在の東京都中央区明石町)
最終学歴:東京帝国大学英文科(現在の東京大学)
芥川龍之介の生涯をおさらい
明治25年3月1日、現在の東京都中央区にて誕生した芥川龍之介。
牛乳販売業を営む新原敏三とフクの長男でした。
まもなく母フクが精神に異常をきたしたことから、母の実家である芥川家に引き取られます。
伯母フキは教育熱心な女性で、龍之介の人格形成に大きく影響を与えた人物でした。
やがてフクが他界すると、フクの実兄の芥川道章の養子に迎えられて芥川姓を名乗ることに。
「芥川龍之介」は戸籍上の名前であり、本名です。
成績優秀だった龍之介は東京府立第三中学校を卒業後、第一高等学校に無試験で入学。
同級生には生涯の親友となる菊池寛、井川恭らがいました。
大正2年には難関の東京帝国大学文科大学英文学科に進学。
在学中に菊池寛らと第三次『新思潮』を創刊し、初の小説『老年』を発表。
人間のエゴを描き、代表作のひとつになった『羅生門』は大正4年の作品です。
第四次『新思潮』で発表した『鼻』が夏目漱石に激賞され、激励の手紙を受けとったことは大きな自信になったようです。
大学卒業後は海軍機関学校の嘱託教官として英語を教えるかたわら、『芋粥』、初の短編集『羅生門』などを発表。
文壇の寵児として次々と執筆依頼が舞い込むようになりました。
教職を辞したあとは出社義務のない社員として大阪毎日新聞社に入社し、創作活動に専念。
この翌年に海軍少佐・塚本善五郎の娘の塚本文と結婚。
大正10年頃から神経衰弱、腸カタルなどを患い、作品数は減少していきます。
晩年は人間社会を批判した『河童』、孤独と絶望を描いた『歯車』など、生きることへの疑問を投げかける作風が目立つようになりました。
大正15年には神経衰弱や不眠症が悪化して療養。
昭和2年7月24日、睡眠薬による服毒自殺でこの世を去りました。
35歳でした。
芥川龍之介の遺書
龍之介が命を絶ったのは、『続西方の人』を書き上げた雨の未明のことでした。
場所は田畑の自宅です。
使用した薬については異説もあり、青酸カリによる自死とする見解もあります。
また、死の直前に自殺をほのめかす発言をしていたともいわれており、早期発見を想定した狂言とみる向きも。
仮に狂言自殺が事実だとすれば、発見が遅れたために心ならずも命を落としたことになります。
遺書としては文夫人や菊池寛らに宛てた手紙がありますが、『或旧友へ送る手記』も久米正雄に宛てた遺書とされていますね。
『或旧友へ送る手記』には「僕はこの二年ばかりの間は死ぬことばかり考へつづけた」とあり、自殺を決意していたことや薬品を入手しようとしていたことが記されています。
この記述を信頼すれば、龍之介はかねてより自殺を計画していたとみるのが自然でしょう。
文夫人が「お父さん、よかったですね」と亡骸に語りかけたという話も伝わりますが、何より耳目をひいたのは、自殺の動機として書き残した「将来に対する唯ぼんやりした不安」という言葉でした。
晩年の作品群には、世をはかなむ心境が映し出されているのも気になるところです。
龍之介の自殺が報じられると、あまりの衝撃に若者たちの後追い自殺が相次いだといいます。
友達の菊池寛と谷崎潤一郎
第一高等学校時代からの親友であった菊池寛は、龍之介の死に号泣し、友人総代として弔辞を読みました。
『文藝春秋』の創刊者であり、のちに文藝春秋社を設立した作家です。
菊池寛のエピソード集。競馬・麻雀・将棋好き。死因の狭心症、子孫について
龍之介が没して8年がたった昭和10年には、亡き友の名を冠した芥川龍之介賞を創設。
直木賞と並び、日本でもっとも有名な文学賞として今も社会的関心をも集めています。
本日3月6日は作家 #菊池寛 さんの命日です。1888-1948 享年59歳 香川県出身。明治〜昭和にかけて活躍した作家で実業家でもありました。「#文藝春秋」を創刊し、#芥川賞、#直木賞 を設立した文学界の大御所として知られています。https://t.co/ljojN4y7ke #追悼 #命日 #RIP #作家 #芥川龍之介 pic.twitter.com/Du9QTF0iNg
— みき⭐️ (@digimem2020) March 5, 2020
同じく親交の深かった谷崎潤一郎とは文学論争を巻き起こしたことがありました。
その論点は、小説の真髄は詩的な芸術性にあるのか、それとも筋の面白さにあるのかというもの。
芸術性至上主義の龍之介と、ストーリーに重きをおく谷崎潤一郎。
これは取りも直さず、両者の小説の特徴を反映した主張でもありました。
小説に対するそれぞれの姿勢が伝わってきますね。
実は、谷崎作品は初読みだ。
え?こんなに読みやすくて面白いの?
あっという間に読めてしまった。モラル云々などいうものはとりあえず置いておいて、このバカバカしさを楽しんだもの勝ちだな。
作者の他作品も読んでみたい。 pic.twitter.com/PQ6dZ7UcgW
— リリカ @読書📙 (@MiiLove777) October 7, 2020
興味深い論争なのですが、どちらの意見が正しく、どちらの意見が誤りという結論をだせるものではないでしょう。
つまるところ、作者が作品の中に落とし込む「詩的な芸術性」と「筋の面白さ」の配分の問題という気がします。
ちなみに、この論争は数か月にわたり続いたものの、龍之介の自殺により結論がでないまま幕を閉じることになりました。
近代短編小説のさまざまな可能性を試みた芥川龍之介。
その死は、ひとつの時代の変わりめを告げる事件でもあったように思えます。
関連記事
芥川龍之介の子供は3人の息子。妻・文との馴れ初め。恋人まとめ&子孫も有名人

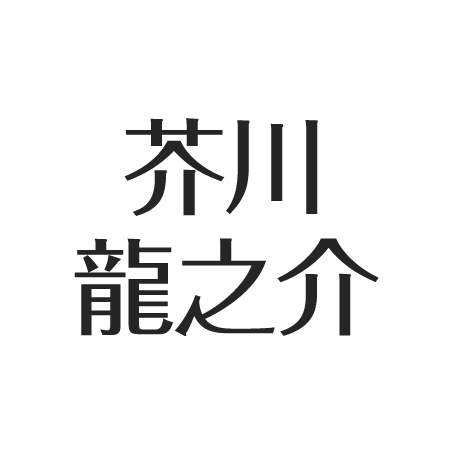
コメント