婦人雑誌「青鞜」の創刊者である平塚らいてう(ひらつか らいちょう)。
大正期の女性思想家として有名ですが、具体的な活動はあまり知られていないかもしれませんね。
今回はまずらいてうの子孫、夫を確認します。
さらに与謝野晶子との違いを、思想とフェミニストとしての主張から比較しましょう。
平塚らいてうのプロフィール
本名:奥村明(おくむら はる)
生年月日:1886年2月10日
死没:1971年5月24日
身長:不明
出身地:東京都
最終学歴:日本女子大学校家政学部(現在の日本女子大学)
平塚らいてうの子孫
まずらいてうの子孫を確認します。
らいてうは、長女の築添曙生さんと長男の奥村敦史さんをもうけました。
曙生さんの娘で、らいてうの孫にあたるのが、女優でダンサーの築添美可さん。
アングラ劇団「黄金劇場」を経て、「炎美可(ほのお みか)」の芸名で、日劇ミュージックホールのヌードダンサーとなりました。
昨日の公演に平塚らいてうのお孫さんたちがお見えになりました! 左は長男・敦史さんの息子の奥村直史さん、真ん中は作・演出の永井愛、右が長女・曙生さんの娘の築添美可さんです。楽屋にもおいでいただき、キャスト一同感動! らいてうさんがぐっと身近に感じられました。 pic.twitter.com/xHyriOBMKT
— 二兎社 OFFICIAL (@Nito_sha) December 9, 2019
曙生さんの息子・築添正生さんは、彫金作家でした。
2010年に亡くなり、翌年に遺稿集『いまそかりし昔』が出版されています。
またらいてうの長男・敦史さんの息子は、心理療法士の奥村直史さん。
早稲田大学で心理学を修め、心理療法士や東洋学園大学非常勤講師として活動。
著作『平塚らいてう-孫が語る素顔』で、等身大のらいてうについて詳述しました。
実は非社交的だったらいてうには、「自己表出障害」があったと述べるなど、心理学者らしい見方で祖母を分析しています。
らいてうの子孫は、各分野でマルチに活動していたことがわかりましたね。
平塚らいてうの夫
らいてうの夫は、5歳年下の洋画家・奥村博史です。
100年以上まえ。
封建的な家長制度、結婚制度に疑問を感じていた平塚らいてうが恋人の奥村博史に送った結婚に関する8つの質問。
そして二人は結婚生活ではなく「共同生活」を始める。 pic.twitter.com/PlYmCjD4wd— 進士 素丸 (@shinjisumaru) January 10, 2021
彼女が出会った当初は、画家志望の病弱な青年でした。
らいてうは茅ヶ崎の南湖院に肺結核で入院中の奥村と恋仲になり、26歳の時に夫婦別姓で事実婚に至ります。
一度彼がらいてうに別れの手紙を出した際、文中でつばめが飛んできて別れることに触れました。
その手紙をらいてうが「青鞜」で発表した結果、「つばめ」が流行語になり、女性より年下の恋人を「つばめ」と呼ぶようになります。
2人は結局、いったん別れた後によりを戻し、長年寄り添いました。
らいてうは奥村の「まことにその人らしく、自然な、率直な」回答に、決心はいよいよ固まったと言います。
奥村は洋画家であり、また金工家として宝飾デザインなども手掛けますが、そのきっかけは「妻の指を飾るふさわしい指輪」を作りたかったからだそう。
二人は晩年まで寄り添いました。 pic.twitter.com/13trPJDuGH— 進士 素丸 (@shinjisumaru) January 10, 2021
当時にしては珍しく、「家」に縛られない、自由な恋愛を謳歌したカップルだったのです。
与謝野晶子の違いは?思想、フェミニストとしての主張
平塚らいてうはよく、『みだれ髪』で有名な歌人・与謝野晶子と混同されるようです。
しかし2人は「母性保護論争」を盛んに議論していたフェミニストであり、主張は似ているどころか真逆でした。
「母性保護論争」は女性の出産と育児、仕事に関する論争。
私生活で晶子は、12人もの子供を産んでいます。
一方でらいてうは、2人しか子供を産んでいません。
単純に考えれば、晶子は母性を重視し、らいてうは母性より女性の自立を重視しているように思えますね。
しかし実際に2人が抱いていた思想は逆で、晶子は女性の自立、らいてうは社会による母性の保護を訴えたのです。
平塚らいてう「国家は女性を母として保護するべき」
与謝野晶子「いやそれ男女平等ちゃうやん」
山田菊栄「社会主義革命待ったなし」 pic.twitter.com/CjjJtfnGmT— 青識亜論(せいしき・あろん) (@BlauerSeelowe) April 6, 2019
子育てに苦労した晶子は、女性は母性に頼らず、もっと自立しなければならないと主張します。
女性が自立能力を持ちながら子育てに専念し、夫と国に保護される状態を批判。
子育てする女性を保護する制度自体は必要と認めつつも、保護を当てにして自立しない女性の在り方に一石を投じます。
いわば「国の妾」になりたがる女性の自立心のなさを指摘したのです。
一方らいてうは、「母親たちを社会で支えよう」と訴えました。
晶子の望むように女性が自立して全員が労働市場に赴けば、労働力が過剰になってしまいます。
結果的に男女労働者が競争し、平均賃金が低下すれば、労働者の生活が困窮しかねません。
だからこそ女性が育児に専念できるよう、社会で支えるべきだと主張したのです。
2人の意見は真逆ですが、それぞれの主張に基づいた制度が今日整えられています。
例えば働く女性が健康保険や失業保険に入るのは、晶子の主張した「自助努力」の成果といえますね。
しかし保険制度を整えているのは税金という点には、らいてうの「社会が女性を支えるべき」という思想が組み込まれています。
2人の主張はそれぞれ的確さとあいまいさが入り混じり、どちらが正しいとは断定できません。
しかし生き方が多様化する現代において、2人の主張の中から参考になる点は、積極的に活用すべきですね。
関連記事
津田梅子の性格。アメリカ留学で英語力は?生い立ちと経歴、数奇な生涯
下田歌子の生涯。津田梅子は同志&和歌、明治天皇との関係。袴スタイルの考案者

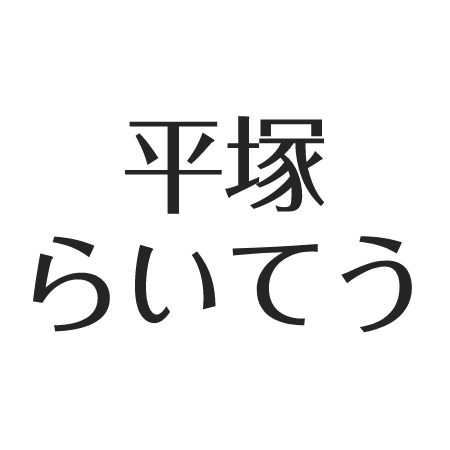
コメント