江戸幕府最後の将軍・徳川慶喜(とくがわ よしのぶ)。
大河ドラマ『青天を衝け』の放送によって、慶喜の家族にも注目が集まっているようですね。
今回は慶喜の父と母、弟で最後の水戸藩主だった徳川昭武(とくがわ あきたけ)についてご紹介します。
また巣鴨の屋敷跡についても見ていきましょう。
徳川慶喜のプロフィール
幼名:松平七郎麻呂(まつだいら しちろうまろ)、のちに松平昭致(まつだいら あきむね)と改名
生年月日:1867年1月10日(慶応2年12月5日)
死没:1913年11月22日
身長:推定150cm前後
出身地:江戸小石川
最終学歴:弘道館
徳川慶喜の父
まず徳川慶喜の父をご紹介します。
ついに!栄一と慶喜公が出会いましたね!これからどんどんおかしれぇことになる予感。慶喜公の「快なり!」も聞けて泣きそうです…そして、撮影のため出張中だった #草彅剛 さん使用品の陣笠が #北区大河ドラマ館 に戻ってきました!おかえりなさい!#青天を衝け #渋沢栄一 #吉沢亮 #徳川慶喜 pic.twitter.com/q3Gg9SoW09
— 渋沢×北区 青天を衝け 大河ドラマ館【公式】 (@shibusawakitaku) May 16, 2021
慶喜は江戸小石川にある水戸藩の上屋敷で、9代目藩主・徳川斉昭(とくがわ なりあき)の息子として生まれました。
斉昭は「烈公」と呼ばれ、激動の幕末を荒々しく生き抜いた人物です。
『青天を衝け』では、竹中直人さんが演じ、「斉昭本人にそっくり」と話題になりましたね。
烈公と竹中直人さん
本当に似てるな〜‼️
来年の大河青天を衝け本当に楽しみだし😃✨
NHKさんナイスな配役👍👍👍#青天を衝け #徳川斉昭 #竹中直人 pic.twitter.com/FKrMc2kj2S— かなぶん (@knzwysnr1) November 28, 2020
歴史に疎くても
大河「青天を衝け」はドラマとして実に面白い徳川斉昭を演じる竹中直人
この役は斉昭の魂が憑依したかと思えるほどの激似 pic.twitter.com/gVL2iKmKDt— ゆうぞう (@estoes_unrobo) March 20, 2021
斉昭は前藩主だった兄の斉脩(なりのぶ)が早世したため、兄の養子となって藩主に就任しました。
就任に際し、門閥派の重臣たちは、11代将軍・家斉(いえなり)の息子を迎えようとしました。
将軍の息子を藩主に据えることで、幕府からの支援を期待できるためです。
すると斉昭派の藩士40人が、無断で江戸に入り、陳情して騒ぎを起こします。
その中には、のちに斉昭の腹心となる藤田東湖や武田耕雲斎もいました。
結果的に斉脩の遺書が見つかったため、斉昭が藩主に就任したのです。
最終的に斉昭は幕府での政治にも関与しましたが、井伊直弼を敵に回したことで謹慎処分となり、政治生命を絶たれてしまいます。
晩年は不遇だったようですが、政治家としては優れた手腕を発揮したことも事実です。
水戸藩主となった翌日、藩政改革を表明し、庶民から年貢を無理やり取り立てる政策を否定。
「愛民専一」を謳い、庶民に寄り添う政治を目指したのです。
下級藩士に対しても、政治上の意見表明を許可しました。
同時に贅沢や遊興を禁じ、彼自身も質素な木綿着物をまとっていたそうです。
また藤田東湖や武田耕雲斎ら、下級武士であっても有能な人材を登用。
彼らは旧来の「門閥派」に対し、「改革派」と呼ばれました。
また斉昭は農民たちと交流しながら、飢饉への備えとして雑穀の貯蔵を奨励し、農村の救済に尽力。
彼は水戸藩の派閥闘争が生じる原因を作った人物でもありますが、庶民にとっては理想の君主だったのでしょう。
最後は失脚し、心筋梗塞とされる病で60年の生涯を終えましたが、本来はより長く活躍できた人物だったかもしれませんね。
徳川慶喜の母
家斉は藩主となった翌年の1830年(文政13年)、皇族・有栖川宮(ありすがわのみや)家の吉子女王(よしこ じょおう)と婚姻。
吉子は皇族の末娘で、当時としては高齢の27歳だったため、晩婚でした。
自身もそれをわきまえていたため、後継ぎを作る自信がなく、斉昭に側室をつけることを望んだそうです。
しかし斉昭は愛妻家だったようで、吉子の元へ通い続けます。
結果的に七男の慶喜を含む、3男1女に恵まれました。
ところで慶喜は鳥羽伏見の戦いの際、大坂城から敵前逃亡したことで知られています。
幕府軍敗退の原因になったとして、彼の汚点ともいわれる敵前逃亡ですが、彼が逃亡したのは母・吉子の影響が大きかったようです。
母が皇族出身のため、「朝廷に歯向かいたくない」という思いから、逃亡した可能性が高いといいます。
さらに戊辰戦争で官軍を率いた熾仁親王(たるひとしんのう)は、母方の祖父のひ孫にあたる人物でした。
「親孝行」を重んじる水戸学を叩きこまれた慶喜にとって、母の故郷である朝廷を敵に回すことは難しかったのでしょう。
弟は最後の水戸藩主
慶喜の弟は、水戸藩第11代にして最後の藩主・徳川昭武です。
1910年7月3日、徳川昭武が亡くなりました。
15代将軍徳川慶喜の弟であり、慶喜の名代としてパリ万国博覧会に出席し、ナポレオン3世とも会談しました。
写真撮影に熱心で、維新後は兄の慶喜とよく撮影を楽しんだようです。
ちなみに、昭武のパリ万国博覧会の一行には渋沢栄一も随行していました。 pic.twitter.com/YSUMd4xKYY— 東京歴史倶楽部 (@rekishiclub) July 3, 2020
14歳で慶喜の名代となり、パリ万博に派遣されました。
さらにヨーロッパ各国を訪問していましたが、明治維新が起きたため、パリでの留学生活を断念。
帰国したのち、最後の水戸藩主となりました。
政治よりも芸術や写真を好むハイカラな文化人だったようです。
1884年(明治17年)には、千葉県松戸市に邸宅「戸定邸(とじょうてい)」を建て、移り住んでいます。
#戸定邸
草彅君の慶喜「快なり」良かったですよね😊。
こちらは千葉県にある慶喜の16才違いの弟、最後の三戸藩主、徳川昭武の邸宅。明治期の徳川家の住まいということで、江戸時代から比べれば著しく規模が縮小されてるらしいが、そうはいっても時が時なら将軍に就いてたお方!やっぱり広いです。 pic.twitter.com/XCor8iRVed— TouToo (@toutoo12345) May 17, 2021
戸定邸は「旧徳川昭武庭園」として公開され、2015年に庭園が国の名勝に認定。
広々とした芝生や、緑豊かな常緑広葉樹林、遠くに富士山を望む借景がたかく評価されています。
昭武は早々に隠居し、自然豊かな地で、狩猟や写真を楽しみながら余生を送ったのでしょう。
ゆかりの巣鴨・屋敷跡
慶喜ゆかりの観光地は東京都豊島区の巣鴨にもあります。
彼は61歳から巣鴨の邸に暮らし始めました。
庭には故郷の水戸にちなんだ梅林があったそうです。
屋敷と庭は現存しておらず、今は記念碑が建っています。
徳川慶喜巣鴨屋敷跡地‼️
明治に巣鴨にも住んでいたのねー。
まさか、山手線とすこーし縁があるとは意外だったなぁ。#明治維新150年#幕末#徳川幕府 pic.twitter.com/oHcpyCxs1T
— ビビる大木 (@bibiruookichan) July 10, 2018
ただ彼が巣鴨に暮らした期間は短いものでした。
転居から4年後には文京区小日向に移り住んだそうです。
理由は山手線の開通が決まったため。
電車の騒音を嫌って、巣鴨を去ったそうです。
慶喜も弟と同じく、静かな土地で、自然や趣味を楽しみながら暮らしたかったのでしょう。
彼や家族の人柄を知ることで、大河ドラマをより一層楽しめるかもしれませんね。
徳川慶喜、子孫の現在。ひ孫はカメラマン。家系図は皇族や松平家の系譜
徳川慶喜の正室、嫁は美賀子。篤姫とは不仲?多くの側室、大奥との関係

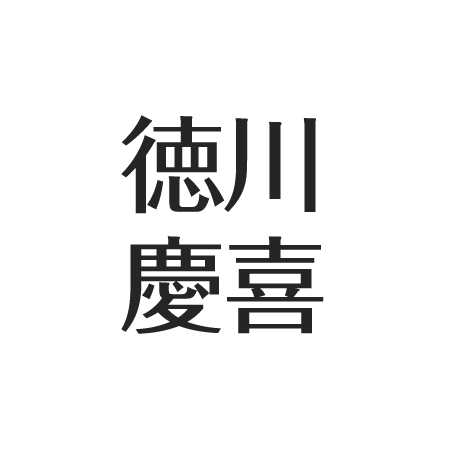
コメント