大河ドラマ『青天を衝け』の草彅剛さんの好演もあり、ここにきて注目が集まっている徳川慶喜(とくがわよしのぶ)。
言わずと知れた江戸幕府最後の将軍ですが、その人物像についてはよく知らないという人もいるのではないでしょうか。
今回は幼少の頃からたしなんでいた絵やフランスとの深い関係、人柄など雑学的な慶喜の一面をご紹介します。
ドラマに登場する家臣たちやエピソードも気になりますね。
徳川慶喜のプロフィール
幼名:松平七郎麻呂(まつだいら しちろうまろ)、のちに松平昭致(まつだいら あきむね)と改名
生年月日:1867年1月10日(慶応2年12月5日)
死没:1913年11月22日
身長:推定150cm前後
出身地:江戸小石川
最終学歴:弘道館
徳川慶喜作の絵には傑作も
約700年におよぶ武家政権に自ら幕を引き、日本史上最後の征夷大将軍となった徳川慶喜。
76年の人生のうち、将軍職にあったのはわずか1年でした。
まるで江戸幕府に引導をわたす役目を託されたかのような人物ですね。
戊辰戦争も終結した明治2年(1869)、謹慎を解かれた慶喜は静岡の元代官屋敷に移り住むことに。
数えで33歳という年齢で、隠棲ともいうべき第二の人生がはじまります。
以降は旧幕臣や世間との関わりを極力断ち、趣味人としての日々を謳歌。
多芸で凝り性の慶喜ですが、その芸術的感性を今に伝えるのが油絵でしょう。
絵は幼少時代から好んで描いていたようで、一橋家にいた頃は奥絵師に山水画を学んだことも。
山水画以上に夢中になったのが洋画の油絵であり、旧幕臣の画家・中島仰山に教えを請うたそうです。
慶喜の作品には、ヨーロッパの田園を背景に描いた風車や湖畔にある石造りの建物など、見たこともない外国の風景画が。
晩年の高祖父、徳川慶喜公の写真
草なぎさん、雰囲気といい素晴らしい演技力だと思います。
瞳の奥の思慮深さ。
でも草なぎさんの方がシュッとしててカッコ良いかも。20%増し。
個人的ツボはオデコ^^;#青天を衝け#徳川慶喜公#大河ドラマ#草なぎ剛さん#ソックリ pic.twitter.com/BeJAxnG6lq— 山岸美喜 (@yamagishimadam) March 5, 2021
それらの落ち着いたモチーフはもとより、のびのびしたタッチや色彩感覚は激動の時代の最高権力者であったことを一瞬忘れそうになります。
当時は画材が調達できなかったため、絵の具やキャンバスなどは手作りしていたそうです。
徳川慶喜とフランスの深い関係
徳川慶喜がフランスの軍服姿で写っている写真を見たことがある人もいるでしょう。
この軍服はナポレオン三世から贈られたもの。
幕府は西洋式の軍隊を創設するためにフランスの軍事顧問団を招いていました。
新しいもの好きで好奇心旺盛な性格も手伝ったのか、駐日公使ロッシュから伝え聞く西洋の情報に慶喜は心をくすぐられたよう。
自らフランス語を学びはじめ、水戸徳川家の弟やその妻にもフランス語を習うようにすすめました。
フランス料理やワインまで大好きになった将軍は、人々から「フランスかぶれ」と揶揄されたほど。
フランスの支援を受けていた幕府にとって、当然フランスは友好国でした。
やがて鳥羽伏見の戦いがはじまると、フランスは軍隊や武器の提供などの軍事的支援を申し出ます。
ところが慶喜はなんとこれを拒絶。
なぜなら、西洋の列強が清やインドを植民地にしたことや、南北アメリカ大陸を侵略し、アフリカから多くの人を連れ去って奴隷にしていたことを知っていたから。
もしフランスの支援のもとに戊辰戦争に勝利すれば、日本の領土は割譲されるか、植民地支配されていた可能性も否めません。
慶喜がなんとしてでも避けたかったのは、内戦に乗じた諸外国の介入だったのでしょう。
徳川慶喜の人柄を分析
つぎに人柄をみていきましょう。
名君なのか、暗君なのかで評価が極端に分かれがちなのも徳川慶喜の大きな特徴。
その言動は真意をはかりにくく、性格も一筋縄ではいかないよう。
性格や言動が単純でないのは、複雑な血筋も関係しているように思えます。
父は水戸藩主・徳川斉昭、母は有栖川宮織仁親王王女・吉子女王。
慶喜は徳川家と朝廷の血を受けた将軍でした。
両者が敵対した場合、はたして片方を完全に敵とみなすことができるのか。
徳川慶喜といえば、最も真意をはかりかねるのが鳥羽伏見の戦いでの「敵前逃亡」。
幕府軍に徹底抗戦を命じつつ、自身は朝敵になることをおそれたのか、江戸に退却。
この総大将としてのあるまじき行為が、臆病者と解釈される大きな理由となっています。
しかし一方で、慶喜が新政府軍に恭順の意を示したことで江戸は火の海にならず、諸外国の脅威から日本を守る結果にも。
慶喜を先見の明がある優れたリーダーとみなし、悪評に一切の弁明をしなかった人柄に敬意を示す人々がいるのも事実です。
上野に展示してあった徳川慶喜公の写真がどストライクだったので控えめに言ってお仕えしたい。めっちゃ聡明で能力高そう。 pic.twitter.com/04hS4vYVVg
— 水晶 (@kokutenkyou) May 20, 2018
幼少期から冷静で頑固な性格だったといわれ、「強情公」とも呼ばれた慶喜。
どこか冷めたマイぺースな性格は、明治期の隠棲生活にも表れていたように思えます。
俗世間との交渉を断ち、政治的野心をもたず、趣味に没頭し、旧家臣の困窮にも無関心。
これらは良くも悪くも自分主義。
将軍職に擁立された際も、内心では貧乏くじを引かされたと歯がみしたかもしれません。
徳川慶喜の家臣・渋沢栄一とのエピソード
『青天を衝け』の主人公で、日本資本主義の父と呼ばれる渋沢栄一は、かつて慶喜に仕えた家臣でした。
やがて慶喜の将軍就任により渋沢も幕臣に。
二人はどのような関係にあったのでしょう。
渋沢栄一を見いだして推挙したのは一橋家家臣・平岡円四郎。
こちらは堤真一さんが演じていますね。
農民身分から一転して武士の身分を手に入れた渋沢は、慶喜の器量に惚れ込み、しだいに認められていくことに。
時代が明治に移ったあとも、渋沢は静岡で隠棲する慶喜の数少ない面会の相手でした。
二人の交流は慶喜が死去するまで続くことになります。
#志茂田景樹 先生、いつもありがとうございます🤗 #青天を衝け#渋沢栄一 #徳川慶喜 #草彅剛
草なぎ慶喜が奥行き深く新鮮な味を出している 参与会議での島津久光を凍りつかせた演技は圧巻だった 明治維新に入るまでは吉沢栄一より草なぎ慶喜のほうが存在感が光る https://t.co/JLhnoShdK3— つばさ🤗 NAKAMA🐱midnight🦢凪沙📕 💞map (@mPqBY6QAjnwuyXV) May 18, 2021
慶喜の名誉の回復に腐心していた渋沢は、のちに『徳川慶喜公伝』を編纂。
渋沢いわく、章を脱稿して慶喜のもとへ持参すると、丁寧に目を通し、時には記述の訂正を望むこともあったそう。
後世に残る自身の伝記だけに、自らのイメージの調整をはかっていたことがうかがえますね。
将軍就任前後の数年間で、平岡円四郎を含めた慶喜の家臣団のうちの3名が暗殺されているのですが、こうしたブレーンがみな存命であったなら、慶喜の内政外交はどうなっていたのでしょう。
また一般の人間なら、側近を失った悲しみや不安、さらには自らに迫る死の恐怖などにさいなまれて、とても倒幕勢力と対峙することなどできそうにありません。
このあたりにも徳川慶喜という人物のたぐいまれな冷静さや胆力が表れているような気がします。
徳川慶喜、子孫の現在。ひ孫はカメラマン。家系図は皇族や松平家の系譜
徳川慶喜の正室、嫁は美賀子。篤姫とは不仲?多くの側室、大奥との関係

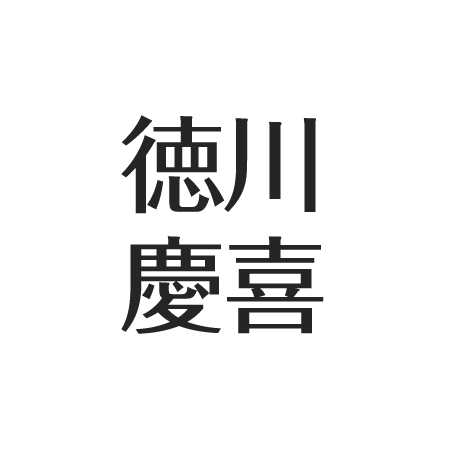
コメント