世界の映画人がリスペクトする巨匠・小津安二郎(おづ やすじろう)監督。
「小津調」と呼ばれる映像美学で、昭和の日本人の家族像を端正に描き続けた映画監督です。
今回は、その独創的な映画づくりのスタイル、名作、また戦後の小津作品の代名詞となった女優・原節子さんのお話です。
名監督・小津安二郎と女優・原節子
戦前から戦後の復興期にかけて、原節子さんは名だたる巨匠の映画に出演した銀幕の華でした。
代表作に黒澤明監督の『わが青春に悔なし』、主題歌も大ヒットした今井正監督の『青い山脈』、小津安二郎監督の『東京物語』があります。
「5センチ眼(まなこ)」と呼ばれたぱっちりとした目に、気品をたたえた清潔感。
演技力を疑問視する声もありますが、こんなエピソードが残っています。
原さんのデビュー作で、監督がある指示を出したときのことです。
それは、相手を遠くから見かけて呼びかけるというものでした。
すると15歳の新人女優は監督にこう聞き返したといいます。
「その前に二人は何回くらい会っているのでしょうか?」。
監督は感心し、大女優を予感したとのこと。
小津安二郎監督も原節子さんを高く評価し、自作品に起用し続けました。
『晩春』『麦秋』『東京物語』と続く紀子3部作は、小津監督の絶頂期を作っていきます。
同じく小津作品の顔である笠智衆さんの著書には、原さんがほとんどNGがなく、人を滅多に褒めない小津さんも絶賛していたとのこと。
原節子さんはまた、生き方そのものが伝説となった女優でもありました。
42歳での突然の引退。
小津監督の他界に号泣し、葬儀には本名の會田昌江で参列しました。
そして、2015年に死去するまで独身を通し、表舞台に姿を見せないスタンスを貫いたのです。
そのスタンスは、伝説の女優となった一因となりました。
「豆腐屋」小津安二郎の誇りと美学 構図へのこだわり
日本家屋の畳に座り、動きのないまま台詞をやりとりすることの多かった当時の日本映画。
そうした光景をスクリーンで魅力的にみせることは課題でした。
小津監督の映画を観ていると、まるで絵画を眺めているような感覚にとらわれることがあります。
撮影のさい、監督はいつもカメラを自らのぞいて構図を決めていました。
例えば登場人物の背景に柱やふすまがあります。
これらが作り出す縦の線を巧みに利用して、スクリーンの中にもうひとつのフレームを設定するのです。
このフレームの中に人物が収まることで、視覚的に心地よい安定感が生まれたといわれています。
小道具の配置にも徹底してこだわりました。
一見無造作に置かれた食卓の上の食器やビール瓶も、実は計算し尽くされていたのです。
時にはそれぞれのグラスに残る液体の高さまで揃えるという徹底ぶり。
そして小津調構図の極めつけ、ロー・ポジション。
カメラを低い定位置に固定して撮影するため、画面の構図が変わりません。
調和のとれた構図の中に人物を配置するという、小津監督ならではの美学がありました。
小津作品はいつも同じだという批評に対して、監督はこんな名言を残しています。
「どうかすると、『たまにゃ変わったものを作ったらどうだい』という人もいるが、ボクは『豆腐屋』だと言ってやるんです。
『豆腐屋』にカレーだのトンカツだの作れったって、うまいものが出来るはずがない」
小津安二郎の名作、『東京物語』
『東京物語』は1953年に公開されたモノクロ映画です。
戦後の日本を舞台に、変わりゆく家族観、家族の崩壊、老いと死といったテーマを落ち着いた作風で描いています。
やがてくる核家族時代や高齢社会を見据えていたかのような家族の光景は、むしろ現在の人々にこそ突き刺さるかもしれません。
持ち味のロー・ポジも多用されており、小津監督の集大成ともいえる傑作です。
ちなみに、大ヒットしたドラマ『半沢直樹』の最終回で、香川照之さん演じる大和田常務が自宅で鑑賞していたのがこの映画でした。
『東京物語』は2012年、英国映画協会が企画した世界の映画監督たちが選ぶ名作の1位に選出されています。
日本人の心情を淡々と描き続けた小津安二郎監督。
ドラマティックな作品づくりはせず、畳の上の日本人の目の高さにこだわり、伝統的な日本文化の佇まいを見つめ続けた映画監督でした。
関連記事
小津安二郎の死因とお墓は?愛した鎌倉&妻をもたず生涯独身の理由とは
原節子、マッカーサーの愛人説はデマ。結婚せず旦那や子供はいない&小津安二郎との純愛
原節子ハーフ説。出川哲朗と親戚?兄の死と家族、ドイツ映画に出演
原節子の晩年と引退後。鎌倉、狛江の自宅について。引退理由とは

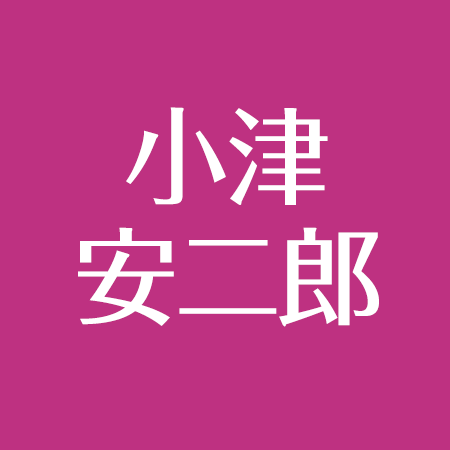
コメント