日本文学史上、川端康成さんに次ぐ26年ぶり二人目のノーベル文学賞受賞者となった大江健三郎(おおえけんざぶろう)さん。
作品世界に多大な影響を与えた長男の光さんはよく知られていますが、今回は次男をはじめ、娘、妻に注目します。
障害をもつ光さんを受けとめて育んだ家族の物語にも迫ります。
大江健三郎のプロフィール
生年月日: 1935年1月31日
没年月日: 2023年3月3日(88歳没)
出身地:愛媛県喜多郡大瀬村(現: 内子町)
最終学歴: 東京大学文学部仏文科
大江健三郎の息子(次男)は大江桜麻
大江健三郎さんは1935年1月31日、愛媛県喜多郡の旧大瀬村で誕生しました。
山あいにある自然豊かなこの村は、のちの作品にもたびたびモデルとして登場しています。
小説家としての才能は東京大学在学中から開花し、デビュー作となった『奇妙な仕事』は新聞の文芸時評で絶賛されて執筆依頼が殺到。
『飼育』により当時最年少の23歳で芥川賞を受賞。
1967年には、大江文学ファンのあいだでも人気の高い『万延元年のフットボール』で谷崎潤一郎賞を受賞。
#読了
【The Silent Cry】
邦題【万延元年のフットボール】
大江健三郎🏆ノーベル文学賞 受賞理由の代表作
地方の周縁文化への意識が下敷
近代化の直前に幕府が米国に使節船を送った1860年と1960年
⭕️構成の緻密さ
寓意と象徴の多用
異次元の文体…
「乗り越え点」文学の傑作#読書 #読了本 pic.twitter.com/5RF5XlVB1X— ジャズと小説🎷🎺 (@jazz_novels) March 24, 2023
1994年にノーベル文学賞を受賞した際は、「生きている私が受賞したのです」という印象的なコメントを残した大江健三郎さん。
日本文学は高い水準にあること、また井伏鱒二さん、安部公房さん、大岡昇平さんが存命していれば彼らが受賞したであろうことも語っています。
そして、彼らの仕事なくして自分の受賞はなかったことなどを述べ、尊敬する先行文学者に敬意を表しました。
#同時代ゲーム#大江健三郎
大江式マジックリアリズムと言えば単純だがそういう風にだけ捉えるのは勿体ない。想像力の束を投げつけられるような作品だが途中から非常に面白くなる。文体が苦手って人は最初はとにかく辛抱すれば開けて来る。
難しく考えずに壮大で知的な空間を楽しんで欲しい。#読書 pic.twitter.com/WieEfsOad3— モンタナS🐵 (@montanas1968) July 31, 2019
大江健三郎さんは長男の光さんをモチーフにした作品を何作も発表しました。
そのため、光さんは読者の間ではよく知られた存在です。
長男誕生の6年後になる1969年には次男の桜麻(さくらお)さんが生まれました。
父と一緒にたびたびメディアに登場していた作曲家の光さんと違い、桜麻さんについては情報がほとんどありません。
東京大学の大学院に在籍していたようですが、2024年現在の状況は不明でした。
娘の情報は非公開。妻は伊丹十三の妹
1967年に誕生した長女の菜摘子さんについても、生年と名前以外はわかりませんでした。
2024年は57歳を迎えることから、家庭をもっている可能性が高いと思います。
妻のゆかりさんは映画監督・伊丹万作さんの長女として1935年2月18日に京都市で誕生。
伊丹十三さんの2歳年下の妹にあたります。
大江健三郎さんと伊丹十三さんは愛媛県立松山東高等学校の同級生。
とても仲のよい友人だったそうです。
おそらくゆかりさんとも高校時代に出会っていたのでしょう。
大江健三郎さんは1959年に東京大学を卒業。
そして、同じ年に成城へ転居しています。
ゆかりさんと結婚したのは、翌1960年でした。
大江光を育んだ家族
学生作家として文壇にデビューし、戦後日本文学界の新しい風として期待を寄せられた大江健三郎さんでしたが、やがて創作に行き詰まりを感じるようになりました。
そんな頃、長男の光さんが知的障害をもって誕生します。
1964年の『個人的な体験』は、わが子の死を願う父親がさまざまな苦悩と葛藤の末に現実を受け入れ、ともに生きていく覚悟をするまでを描いた意欲作。
その人道主義的な内容が高く評価されて、『万延元年のフットボール』とともにノーベル賞への大きな道筋をつけました。
『個人的な体験』#大江健三郎
【精神の衛生】
脳に障がいのある子供を授かる父親の
自我と倫理の物語自由保持からの現実逃避
倫理観からの強迫観念
自己欺瞞との対峙子供を受入れ自己を肯定し
利己から愛他への目覚め《生命を生み育てる》
この責任と覚悟は
無条件に素晴らしい#個人的な体験 pic.twitter.com/TYWurPyz6U— ken (@ken70121871) May 22, 2020
作家として行き詰まりを感じていた自分に力を与え、ノーベル賞をもたらしてくれたのは光さんであることを折に触れて明言してきた大江健三郎さん。
音楽の才能に目覚め、音楽を通して成長していく光さんと、それを見守る家族の姿も、これまでテレビで幾度となく紹介されてきました。
作業所へ通う光さんに付き添っていたのは桜麻さんであり、エッセイ『恢復する家族(かいふくするかぞく)』のあたたかい画はゆかりさんによるものです。
同書では、光さんの苦しみを受けとめて手を携えて生きることで家族もまた癒されていくようすが綴られています。
戦後日本の閉塞感を見つめ続け、現代人の生き方を追求してきた大江健三郎さん。
そのような小説家にとって、障害をもつ子供が生まれるというのはまさに「個人的な体験」であり、その後の文学の方向性を決定づけるものだったに違いありません。
もし光さんが生まれていなければ、別のテーマで創作に取り組んでいたかもしれないと思うと不思議な気持ちがします。
何が作家の内なる才能を刺激して、文学に昇華させていくのかは予測のつくものではないとあらためて感じます。
関連記事
大江健三郎の経歴まとめ。生家は現存。英語がカタカナ?伊丹十三は義兄&死因は老衰
大江光の現在。知的障害と自閉症の噂、兄弟は2人。坂本龍一からの批判とは
井上ひさしの次女と息子は母違い。家族と絶縁、再婚後の生活。生い立ちが壮絶&猫虐待の過去
司馬遼太郎、息子はいるが娘はいない。二人の妻。再婚の経緯&死因は腹部大動脈瘤の破裂
伊丹十三の息子たち。万作と万平の今。妻・宮本信子とのエピソード

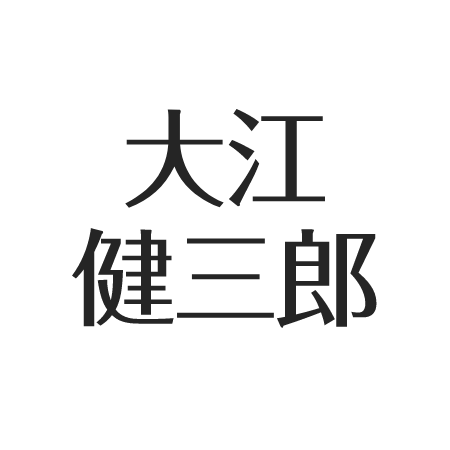
コメント