明治の終わりから半世紀以上にわたって精力的な執筆活動を続けた文豪・谷崎潤一郎(たにざきじゅんいちろう)。
生涯に数十回もの転居を繰り返した引っ越しマニアであり、住居には並々ならぬ美意識を持っていました。
今回は谷崎が愛した神戸芦屋や京都の旧居にスポットをあて、家と谷崎作品の関係性を探っていきたいと思います。
あわせて幼少期を過ごした人形町や猫好きのエピソードもお届けします。
谷崎潤一郎の神戸芦屋の家
明治43年、東京帝国大学の学生だった谷崎潤一郎は『刺青』を発表し、新進作家として注目を集めます。
翌年に授業料未納により大学を中退しますが、以降も東京や神奈川など引っ越しを繰り返しては作品を発表していました。
しかし『刺青』を超えるほどの小説はまだなく、作家としての方向性を模索する時期が続きます。
そんな彼にとって大きな転機となったのが大正12年の関東大震災でした。
箱根でバスの乗車中に激しい揺れに襲われた地震恐怖症の谷崎は、当時は「地震の起こらない土地」といわれていた関西へ家族と移住。
これを機に、神戸芦屋の風土や文化、そこに息づく伝統美に目を向けていくことになります。
従来のモダニズムから日本の伝統美を映し出す作風へと転換したのも関西移住後のことです。
以降、阪神間に腰を落ち着けること21年。
居住した13軒の家のうち、12軒は借家住まいでした。
神戸市にある有名な倚松庵(いしょうあん)は不朽の名作『細雪』のモデルになった家で、細雪の家とも呼ばれる歴史的建造物。
現在地に移築保存されたのは平成になってからです。
谷崎はこの家で『細雪』の執筆にとりかかり、7年を過ごしています。
庵号の由来は最後の妻の名前「松子」から。
「松に寄りかかっている家」という意味で、愛情が感じられますね。
『細雪』は松子夫人とその姉妹と暮らした倚松庵での日々をもとに書かれた小説です。
13軒の家のうち、唯一の持ち家だったのが神戸市の鎖瀾閣(さらんかく)。
谷崎が自ら和風・洋風・中国風を折衷してデザインした豪邸でしたが、阪神淡路大震災で倒壊してしまいました。
古典回帰の『蓼喰ふ虫』はここで執筆されています。
芦屋市にある富田砕花旧居は松子夫人と結婚式を挙げた家。
谷崎のあとに居住したのが詩人の富田砕花でした。
芦屋を舞台にした『猫と庄造と二人のおんな』はここで執筆されています。
兵庫県芦屋市、富田砕花旧居
富田砕花が住む前は、谷崎潤一郎も住んでいたそうです。水・日のみの見学のため、今日は外観のみ見ました pic.twitter.com/fwqXMPM4Qa
— 千船翔子 (@ShokoChifuna) April 7, 2018
谷崎潤一郎の京都の家
京都の賀茂川と高野川が合流するところに下鴨神社があります。
糺の森(ただすのもり)に隣接する石村亭は関西最後の住まいであり、谷崎がもっとも愛したといわれる邸宅です。
『夢の浮橋』の舞台ですね。
谷崎潤一郎がかつて住んでいた「石村亭」。
京都 下鴨神社の東にあるのだけど、門までのアプローチだけでこのオーラ・・・たまんない。。。
少しスケールオーバーしたイチョウの木、
左右に配置された謎の石像、
鳥居のような荒々しいゲート。一般公開はホントたまにしかしていない模様。 pic.twitter.com/qC2TqWbVdn
— 西倉美祝 MinoryNISHIKURA (@MinoryArts) December 3, 2020
ここには昭和24年から昭和31年まで7年8か月居住しました。
売りに出ていたこの家を見て一目で気に入った谷崎は、ほとんど建築時のままで暮らしていたそうです。
当初は水のせせらぎを意味する「潺湲」から潺湲亭(せんかんてい)と名づけられていたのですが、昭和31年に日新電機に譲り渡す際に石村亭に改称。
会社の施設としては名前が堅すぎるという谷崎の提案でした。
現状のままで残してほしいとの言葉は守られ、石村亭は当時の趣や佇まいを残したまま管理されています。
後の潺湲亭と呼ばれることもありますが、その理由はこの邸宅に先立って南禅寺に近い白川のほとりに同じ名の邸宅を持っていたから。
こちらは前(さき)の潺湲亭と呼ばれています。
谷崎潤一郎は人形町生まれの江戸っ子
長く関西を生活の拠点とし、多くの名作を残した谷崎潤一郎は生粋の江戸っ子でした。
明治19年7月24日、現在の日本橋人形町にあった谷崎活版所という黒漆喰の土蔵造りの家で誕生します。
父・倉五郎と母・関の次男でしたが、長男・熊吉が生後3日で他界したため、長男として育ちました。
学業はたいへん優秀で、「神童」と呼ばれていたそうです。
随筆『幼少時代』はタイトル通り、明治中期の東京下町に生まれ育った谷崎が、幼少期の遊び場や下町の商店などをつづった回想録。
谷崎の随筆には、都電、水天宮、人形町通り、佃煮屋のちとせ、鳥屋の玉ひでといったフレーズが登場します。
親子丼を考案し、行列のできるお店で知られる鶏料理店・玉ひでは谷崎も贔屓にしていたようです。
人形町の生家跡には「谷崎潤一郎生誕の地」と書かれたプレートが設置されており、この表示版の「松子書」とは松子夫人の筆によるものという意味です。
猫を愛するあまり剥製に
谷崎潤一郎は著作の中で、いちばん器量のよい動物は猫科の動物でしょうねと語るほどの愛猫家でした。
『痴人の愛』や『猫と庄造と二人のおんな』のように、猫を思わせる女性や猫に振り回される人々が登場する作品もありますね。
#谷崎潤一郎 は猫🐈好き。
愛猫ペルが亡くなった時には、剥製にして飾っていたほど。
しかし、飼っていた猫も ほとんど雌猫。
徹底していらっしゃる(^w^) pic.twitter.com/6sLnH9Fhwt— kappa (@kappa71550292) September 3, 2019
なかでもペルシャ猫を好み、とりわけ溺愛したのがペルという名の猫でした。
書斎には猫を立ち入らせなかった谷崎も、ペルだけは例外でした。
ペルを愛するあまりに死後に剥製にした話は有名です。
当時は今より剥製の置物に寛容な時代だったはずですが、それでも一部では物議を醸したとのこと。
ペルの剥製は芦屋市にある谷崎潤一郎記念館に所蔵されており、特別展の時などに見ることができるようです。
長きにわたりエネルギッシュな創作活動を続け、昭和40年に79歳の生涯を閉じた谷崎潤一郎。
昭和33年よりノーベル文学賞候補に複数回上がっており、ことに昭和35年と昭和39年にはショートリスト(最終候補)の数名に残っていたことが明らかになっています。
三度の結婚と多くの転居は芸術のために求めた変化であり、それを作品に昇華させようとした生きざまだったのかもしれません。
関連記事
谷崎潤一郎は妻・松子を崇拝。千代や丁未子との逸話&佐藤春夫に妻を譲渡
谷崎潤一郎の家系図、母が美人、子供、娘の鮎子について。子孫の現在
泉鏡花は天才? 尾崎紅葉との関係、結婚について。ゆかりの地、金沢と神楽坂
三島由紀夫と家族の家。母親と疎遠だった生い立ち。豪華な家系図とは

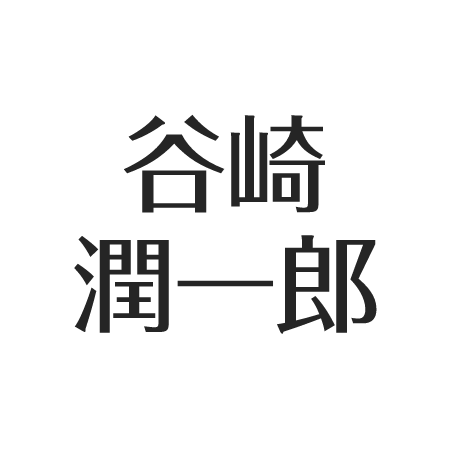
コメント