明治から昭和にかけて活躍し、生涯を通して5万首にも及ぶ歌を残した情熱の歌人・与謝野晶子(よさのあきこ)。
歌の師であり、夫である与謝野鉄幹との間に12人の子供を産みながらも芸術を極め、歌壇に大きな足跡を残しました。
今回は出身や生い立ちを振り返るとともに、家系図に登場する著名な子孫についてみていきます。
与謝野晶子のプロフィール
本名:与謝野志やう(しょう)
生年月日:1878年12月7日
死没:1942年5月29日
身長:不明
出身地:大阪府堺市
最終学歴:堺市立堺女学校(現在の大阪府立泉陽高等学校)
与謝野晶子の子供は6男6女
明治33年(1900)、『明星』に短歌が掲載された与謝野晶子。
当時は「与謝野」ではなく、旧姓の「鳳」(ほう)を用いた「鳳晶子」という筆名でした。
創刊者の与謝野鉄幹と初めて会ったのは、その年の夏のことです。
翌年に晶子は上京し、鉄幹は妻と離婚。
まもなく二人は結婚し、翌年に生まれた長男・光を筆頭に6男6女に恵まれます。
与謝野晶子の12人の子供の名前:
長男・光(ひかる)
次男・秀(しげる)
長女・八峰(やつを)
次女・七瀬(ななせ)
三男・麟(りん)
三女・佐保子(さほこ)
四女・宇智子(うじこ)
四男・アウギュスト
五女・エレンヌ
五男・健(たかし)
六男・寸(そん)
六女・藤子(ふじこ) pic.twitter.com/k89X11HJop— 愛書家日誌 (@aishokyo) December 7, 2022
うち1人は生後2日で亡くなっていますが、23歳から40歳までに12人の子供を出産していますから、少なくとも30年ほどは仕事と子育ての両立が続いたことになります。
そのうえ夫が慶應義塾大学教授の職に就くまでは収入が不安定で、晶子が家計を賄っていたとのこと。
恐るべきバイタリティーですね。
外交官として活躍した次男
晶子の12人の子供の中で最も有名なのは、次男の秀(しげる)かもしれません。
東京帝国大学へ入学した秀は、1928年に法学部政治学科を卒業。
その後は外務省に入り、在フランス日本国大使館の外務書記生となりました。
第二次世界大戦の際は、スペインやスイスなど、ヨーロッパの国々を中心に活躍。
エジプトやスペイン、イタリアでは特命全権大使も務めています。
エジプト🇪🇬現代史の勉強してたら与謝野晶子の名前出てきて草
彼女の次男の与謝野秀がすごい外交官で、戦後まもない頃にエジプトとの関係を重要視してた日本政府の影響で在カイロ初代大使に就任したとか pic.twitter.com/SZoRwSCMkd
— 恵 (@43_ojou) April 11, 2023
1962年からは東京オリンピック大会組織委員事務総長も務めているので、兄弟の中では知名度が高いのではないでしょうか。
歌人の息子が有能な外交官として活躍したのは、すごいことですね。
私生活では、妻は球磨川電気社長などを務めた坂内虎次の娘・道子と1935年に結婚。
その後は2男3女をもうけています。
ちなみに、秀の命日は1971年1月25日。
当時は原子力委員会委員として働いていましたが、肝性昏睡のため66歳で亡くなっています。
珍しい名前の理由
仕事の面で知名度が高かったのは秀かもしれませんが、晶子の子供といえば、真っ先に四男と五女を思い浮かべる人もいそうです。
非常に珍しい名前なので、与謝野ファンの間ではよく話題になっています。
鷗外の子供は有名だけど、与謝野晶子の子供も凄いよね
与謝野アウギュストと与謝野エレンヌって— 胡蝶 (@uturobuneco) December 7, 2013
与謝野晶子の四男の名前はアウギュスト。五女はエレンヌだど知ってこれからはDQNネーム、キラキラネームでなく与謝野ネームと呼ぼうと、思ったのです。
— ナカシマこうだい (@deer_16) October 19, 2013
確かに、現代ならキラキラネームと呼ばれたでしょうね。
すごいインパクトなので、他の子供たちに比べると覚えやすそうです。
こうした名前の由来は、夫妻が影響を受けた海外作品という説もあるのだとか。
アウギュストについては、「考える人」などで有名な彫刻家のオーギュスト・ロダンからとったという噂もあるそうです。
噂がどこまで本当かは不明ですが、事実であれば、やはり現代のキラキラネームに通じるネーミングセンスかもしれません。
外国人やアニメのキャラクターからつけたと思われる難読ネームは、たまに見かけるものですよね。
現代の珍しい名前をもし晶子が見たら、深く共感してくれるのでしょうか。
キラキラネームというと、昔はなかったようなイメージもありますが、実際の歴史はかなり長いのかもしれません。
家系図の子孫に政治家・与謝野馨
家系図に目を向けると、まず注目すべきは夫の鉄幹でしょう。
不倫からはじまった二人の関係は問題視され、誹謗中傷を受けることもありました。
しかし晶子の才能を見ぬいた鉄幹は『みだれ髪』の刊行を決意。
歌人・与謝野晶子を作り上げたプロデューサーはまぎれもなく鉄幹です。
#与謝野鉄幹 は🇯🇵の歌人。日本のロマン主義運動の中心人物である。代表作は「五足の靴」。与謝野晶子は妻にあたる。
鉄幹はプロデュース能力にも長けており、北原白秋、吉井勇、石川啄木らも見出している。創作活動は晶子の方が断然上だったようだ。1935年の本日死去。62歳。 pic.twitter.com/E4Ba0ow81y
— 役立つ情報がいっぱい! (@ijinmeigen001) March 26, 2024
与謝野晶子には兄弟姉妹がたくさんいたようですが、兄の秀太郎は工学者で、「鳳・テブナンの定理」の発見者。
さきほどご紹介した次男・秀と、その妻で評論家の道子夫妻には2男3女が誕生しました。
その長男・馨さんは内閣官房長官、拉致問題担当大臣、財務大臣などを歴任した政治家。
祖父にあたる鉄幹は生まれる前に死去しており、祖母の晶子も4歳の時に死去したため、祖父母は身内というより教科書に出てくる歴史上の人物という感じだと自著で述べています。
次男の達(とおる)さんはレジオンドヌール勲章シュヴァリエを叙勲した国際的な金融家。
三女に詩人で美術評論家の文子さんがいます。
与謝野晶子は堺出身、その生い立ち
与謝野晶子は明治11年(1878)12月7日、堺県堺区(現在の大阪府堺市)にて鳳宗七・津祢の三女として生まれました。
父・宗七は堺の街のほぼ中央を走る大通りに駿河屋という和菓子屋を構える商人。
晶子が誕生した頃は店の経営は傾いていたようですが、9歳で漢学塾に通い、琴や三味線にも親しんでいたとのこと。
10歳を過ぎると父の蔵書の古典や歴史書を読みふけるようになり、家業を手伝いながら和歌を詠むなど多感な少女時代を過ごしました。
自伝『私の生い立ち』には堺時代の生活や心情が細やかにつづられており、与謝野晶子を育んだ時代の風景を味わうことができます。
また堺市にある与謝野晶子記念館では生家・駿河屋を実物に近いサイズで再現。
父・宗七は西洋好みで、建物の2階は洋風の造りになっていました。
晶子が店番をしながら読書にふけったという帳場も再現されており、彼女の文学の出発点を垣間見ることができます。
浪漫派の代表格として情熱的な作品を多く残した与謝野晶子。
歌人・詩人として広く知られますが、その表現活動は詩歌にとどまらず、『源氏物語』の新訳や『八つの夜』などの童話集、評論文と実にエネルギッシュなものでした。
与謝野晶子の経歴まとめ
2018年に生誕140年を迎えた与謝野晶子。
女性ファンが多いといわれる歌人ですが、近年は『文豪ストレイドッグス』の影響もあり、中高生など若年層にも人気が広がっていますね。
22歳で刊行した『みだれ髪』は、女性が性愛を詠うことが常識では考えられない時代に女性の官能をおおらかに表現し、古い因習を打ち破った処女歌集。
歌壇の反発をかいながらも、若者たちの熱烈な支持を獲得します。
また『君死にたまふことなかれ』は日露戦争に従軍した弟を案じて書いた反戦の詩。
軍国主義の日本において激しい非難を浴びながらも、晶子は「まことの心を詠んだだけ」と一歩も退きませんでした。
歌人としての活動のほかに、婦人参政権や女性教育の必要性などを説いた社会活動家の一面ももっています。
関連記事
与謝野晶子、夫・鉄幹とのエピソード。山川登美子との関係。性格は情熱的?死因は病気?
与謝野晶子の弟、詩の意味とは。戦死の噂と日露戦争。スペイン風邪対策を批判
与謝野鉄幹の家系図と子孫。山川登美子&与謝野晶子の三角関係。鹿児島とのゆかり
与謝野馨の息子は優秀、甥が政治家志望。後継者なし?家系図に与謝野晶子&パソコンマニア
国木田独歩、妻2人との結婚や離婚まとめ。孫と子孫の現在(2024)&家系図に芸術家

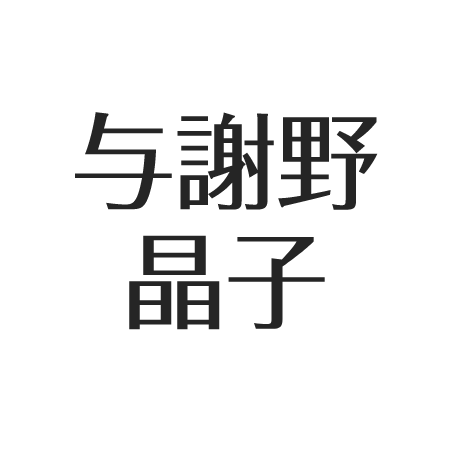
コメント